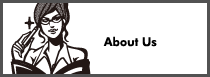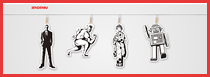以前、山を訪れた親子がワイルドにナイフでハムを切り、そのハムを焚き火にかざすCMがありました。キャッチコピーは『ワンパクでもいい。たくましく育ってほしい!』そう、1970年代に放送されていました丸大ハムのCMです。今でも私の脳裏に記憶されています。(思い出すと何だか懐かしい…タレントまでは覚えていませんが…)
ところで近頃、ワンパクで逞しい子供を見ることが少なくなりました。それどころか大人まで逞しくないから驚いていまいます。
『ワイルドだろぉ~』このフレーズが、昨年の流行語大賞に選ばれたことは記憶に新しいと思います。今の時代にワイルドで逞しい人が減り、同時に『ワイルド』と言う言葉を耳にすることも減りました。だからこの言葉を多くの人が新鮮に感じたのでしょう。私も昨年は巷でよく耳にしましたし、私もたまに使っていました(笑)
ジェネレーションギャップと言えばそれまでですが、今の若い世代は逞しさがなく、チャレンジすることから逃げ、音をあげてしまう人が多いように感じます。そして凹み直ぐに萎えてしまいます。挙句の果てには『草食男子』という言葉まで生まれてしまう始末です。ひょっとすると現代の食生活に関係があるのかもしれませんが…(笑)
これからの時代は今より変化が速く、政治も経済も転換期を迎え大変な時代になると思います。だから何が起きても逞しく生き抜く力が必要なのです。
最近、丸大ハムのあのCMを大量に放送して欲しいと切に願っています。そして丸大ハムを食べる人が増えれば、ワンパクで逞しい大人も子供もきっと増えると思っています。
『落ち込んだら丸大ハムを買って喰え!』
written by ゴンザレス
「何とかする!」私が大ピンチの時、ある取引先の親しい方が私に言った言葉です。その後、彼から連絡があるまで、私は彼を信じて催促の電話を一度もしませんでした。それから2週間ほど過ぎた頃、彼から「何とかした!」と連絡がありました。彼が社内で調整のため走り回り、多くの部署と必死に掛け合ってくれている姿が目に浮かびました。彼とは過去にもお互い大ピンチの時に助け合ったことがあり、今では大きな信頼関係で結ばれています。
「何とかする!」この言葉はその案件が困難や面倒な場合の相談に、相談された側が使う重い約束の言葉です。今回の私の難しい相談に対して、彼が口にした言葉も「何とかする!」その一言でした。そして彼はその重い約束を守ってくれました。難しい約束を守ることで人と人との信頼関係は大きくなります。
困難や面倒な相談に「努力する」などと保険をかけるような話し方をする人や、無理な相談や難しい相談には端から耳も貸さない人もいます。確かに間違えではありません。しかし、できることしか約束しないのであれば、大きな信頼関係をつくることはできないと思います。そもそも困難で面倒な相談は誰にもできるわけではなく、信頼している人にしかできない場合がほとんどです。
もし彼が藁にも縋る思いのときは、私が「何とかする」そう言って必死で彼を助けます。
written by マックス
ある事柄をひとつの角度から見て判断し、結論を出してしまう人がたくさんいます。俯瞰で立体的に全体像を見ないとベストな答えを導くことはできないはずです。
広告業界は特にそのことが顕著に表れる業界で、依頼する側も依頼される側も市場やターゲットを俯瞰で立体的に見ることができないと、アベコベで単純なプランになってしまいます。依頼する側ができなくても、せめて依頼を受ける側ができれば良いのですが…。
クライアントは自社の商品やサービスを基本的に過大評価しているため、まるで競合会社など存在せず、その商品やサービスは多くの消費者が望むものであると思いがちです。もし、そうであれば企画を考え広告などする必要も無く、ほっといても売れするはずです。
市場には多くの競合企業がひしめき合い、また追随企業もすぐに出現します。ターゲットは性別や年齢だけに留まらず、生活環境や生活リズムも多種多様です。また現代はメディアの数も無数に存在し、ターゲットの脳の中にもそれぞれに異なったメディア受信機と記憶装置が備わっています。そこにクリエイティブが関わってくるわけですから、複雑極まりないのです。だから全体像を俯瞰で立体的に見ることが必要です。
「木を見て森を見ず」(You can’t see the wood for the trees)。
一本一本の木に注意を奪われると森全体を見ずに、近視眼的に目の前の木を見てしまいがちです。その結果、森の中で迷って抜け出せなくなってしまいます。
きっと人生も同じで、目の前のことだけに捕らわれるのではなく俯瞰で立体的に見ることで、もっと人生は変わってくるはずです。どんなに苦しい時も視点を変えれば、人生はきっと素敵で楽しく感じるはずです。
written by マックス